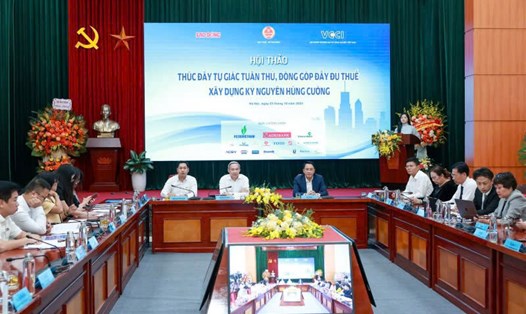ホアン・クアン・フォン氏 - ベトナム商工連合会VCCI副会長: ビジネスリーダーは戦略的経営の一環として税金を考慮する必要がある

「税法を遵守する能力」の概念には、規定に従って期日までに納税するという行為だけではなく、法律を遵守する能力、効果的な会計税務管理システムを組織する能力、税務当局と協力する積極的な姿勢も含まれます。特にベトナムが納税者の自発性と自覚が基礎となる「リスクベースの税務管理」モデルに大きく移行している場合には、この能力の向上が緊急の要件となる。
現在、デジタル化と国際標準の統合により、ベトナム企業の税務コンプライアンス能力は明らかに向上しています。しかし、コンプライアンス体制は依然として「意志と能力」に応じて分断されており、大企業は積極的な税務行政に向かう一方、中小企業は人材、データ、政策の安定性に限界があるため「望んではいるが困難」である。
ビジネスリーダーは戦略的な経営の一環として税金を考慮し、システム、人材、テクノロジーに真剣に投資する必要があります。 「積極的なコンプライアンス」の考え方をトップから根付かせることで、コンプライアンス能力は持続的に強化されます...
フランク・ヴァン・ブランショット氏 – 国際通貨基金IMF財務省上級経済専門家: 低い税/GDP比率は持続可能な開発目標に影響を与える

ベトナムの税対GDP比は2024年に13.1%となり、持続可能な成長を支えるためにIMFが推奨する最低水準の15~16%を大きく下回っている。税金とGDPの比率が低いと、政府がインフラ、教育、社会保障にさらに投資して持続可能な開発目標を達成する能力が制限されるだろう。国際的な経験によれば、金利が 15 ~ 16% の基準を超えている国は、より強力で持続可能な成長を遂げています。
IMFの世界経済見通しと世界政策アジェンダは、世界的に公的債務が増加することに対する差し迫った懸念を指摘しています。さらなる債務の選択肢は狭まっており、さらなる税率引き上げは政治的、経済的に困難であるため、多くの国が「税金問題」に直面している。このような状況において、税務行政の役割はますます重要になります。高い税率だけに依存するのではなく、役人の能力強化、制度改革、コンプライアンスの向上と課税ベースの拡大に焦点を当てて、国内歳入を動員する必要がある。
ブイ・ゴック・トゥアン氏 - デロイト ベトナム、税務・法務コンサルティング サービス副本部長: 企業は税務データを戦略的資産として管理および活用する方法を知る必要があります。

以前は「税務コンプライアンス」が主に規制上の義務を正しく完全に履行することと関連付けられていましたが、透明性のあるデータの時代となった現在、この概念の範囲と意味は大きく変わりました。テクノロジー、データ、開示要件により、税金はこれまで以上に結びつき、シームレスかつ透明になっています。
Deloitte の「Tax Transformation Trends 2025」レポートでは、税務担当者の 57% が今日の税務管理チームには AI とデータ分析のスキルが必要であると考えていると述べています。さらに、94% が、専門のコンサルタントと協力することで、企業の運営コストが削減され、コンプライアンスの品質が向上すると考えています。
したがって、新しい状況において、企業は遵守する必要があるだけでなく、戦略的資産として税務データを管理および利用する方法を知る必要があります。彼らはより迅速かつ正確に意思決定を行い、市場で長期的な優位性を生み出す必要があります...
野口大介氏 – JICA税務プロジェクトチーフアドバイザー:納税の意味を正式な教育プログラムに組み込む

日本では、何十年にもわたる制度、教育、実務の同時発展のおかげで、税金の自己申告・自己納付の制度が社会生活に深く浸透してきました。
税務行政のデジタルトランスフォーメーションが引き続き推進される中、規制や法的手続きの改善に加え、行政機関と納税者の双方が「対話と共通の説明責任の文化」を構築することが重要です。
また、自主的な遵守を促進する最も基本的な要素は租税教育です。
「租税文化、コンプライアンス、市民権の構築」(2021年)と題されたOECD報告書は、租税教育を「社会契約」の理解を強化するための基礎として検討し、納税義務の意味を正式な教育プログラムに組み込むことの重要性を強調した。日本の国税庁は、1963年以来、文部科学省と連携して、学校教育における租税学習の取り入れを推進し、ビジネス研修や地域講座などを通じて租税学習の機会を提供し、長期的に「税を通じて社会に貢献する」という意識を醸成してきました。
金融専門家グエン・ミン・トゥ氏: 市民の誇りを呼び起こし、自覚的な税務コンプライアンスを促進

納税コンプライアンスが文化となるためには、納税コミュニケーションが「義務の宣伝」にとどまらず、シビックプライドを活性化するものに移行する必要があると思います。だからこそ、私は調査官ではなくガイドである「優しい税務職員」のイメージを構築することを強く支持しています。わかりやすい説明、取引カウンターでの正しい姿勢のひとつひとつが、どんなクリップやスローガンよりも強力なコミュニケーションメッセージとなります。
メディアは「どう伝えるか」ではなく、「どうやって聞きたいと思わせるか」です。信頼を植え付け、自覚的な税務コンプライアンスを促進する過程において、私は、これからの時期の税務コミュニケーションは 3 つの原則に焦点を当てる必要があると信じています。それは、押し付けではなく理解です。対立ではなく透明性を。コントロールするのではなく、伴走する。
なぜなら、税金は国民と国家の信頼関係として捉えれば、もはや負担ではなく、文明の象徴となるからである。