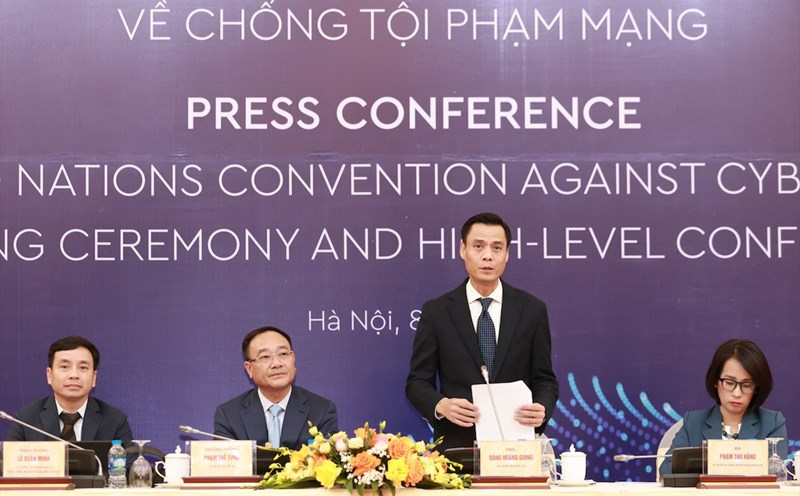以下に、条約の主な内容を 7 つ挙げます。
1. 犯罪化
ハノイ条約の最初の焦点は、加盟国にサイバー犯罪を国内の刑事法制度に組み込むよう要求することです。法的な「グレーゾーン」を撤廃し、刑事訴追の統一基盤を創設するためだ。
この条約は、情報技術システムへの不正アクセス、データ干渉や妨害行為から、サイバー犯罪を目的とした機器やソフトウェアの使用に至るまで、犯罪とみなされるべき一連の行為を明確に特定しています。このほか、詐欺、電子偽造、マネーロンダリング、児童虐待コンテンツや私的画像の配布などの犯罪も取り扱う範囲に含まれる。
この条約はまた、法人の責任、共犯者、共謀または犯罪実行幇助に対処するための仕組み、特に子供や弱い立場にある人々の人権を確保するための原則も規定している。
2. 管轄区域
サイバースペースでは、従来の地理的境界はほとんどなくなり、捜査と裁判の管轄権を決定することが大きな課題となっています。
ハノイ条約は、自国の領土内で犯罪が発生した場合、国外で自国民によって犯された場合、または国益や安全に損害を与えた場合に各国が管轄権を行使できる明確かつ柔軟な規則を定めています。
犯罪者がその国が引き渡していない地域に存在する場合でも、その国は引き渡しを試みることができます。管轄権が重複する状況では、犯罪者が見逃されることを避けるために、当事者は協議し、調整する必要があります。
3. 訴訟対応
サイバー犯罪捜査の大きな課題の 1 つは電子証拠、つまり多くの国で簡単に変更、削除、または散在する証拠です。
この条約により、電子データの保存と取得からユーザー情報の要求、転送中のデータの傍受と監視に至るまで、各国が訴訟システムをこの現実に適応させることができます。
ただし、これらの措置の施行は、プライバシーと個人の自由の保護と並行して行われなければなりません。この条約は独立した司法審査を義務付け、その範囲と期間を制限し、捜査対象者が告訴し公正な裁判を受ける権利を保障するものである。
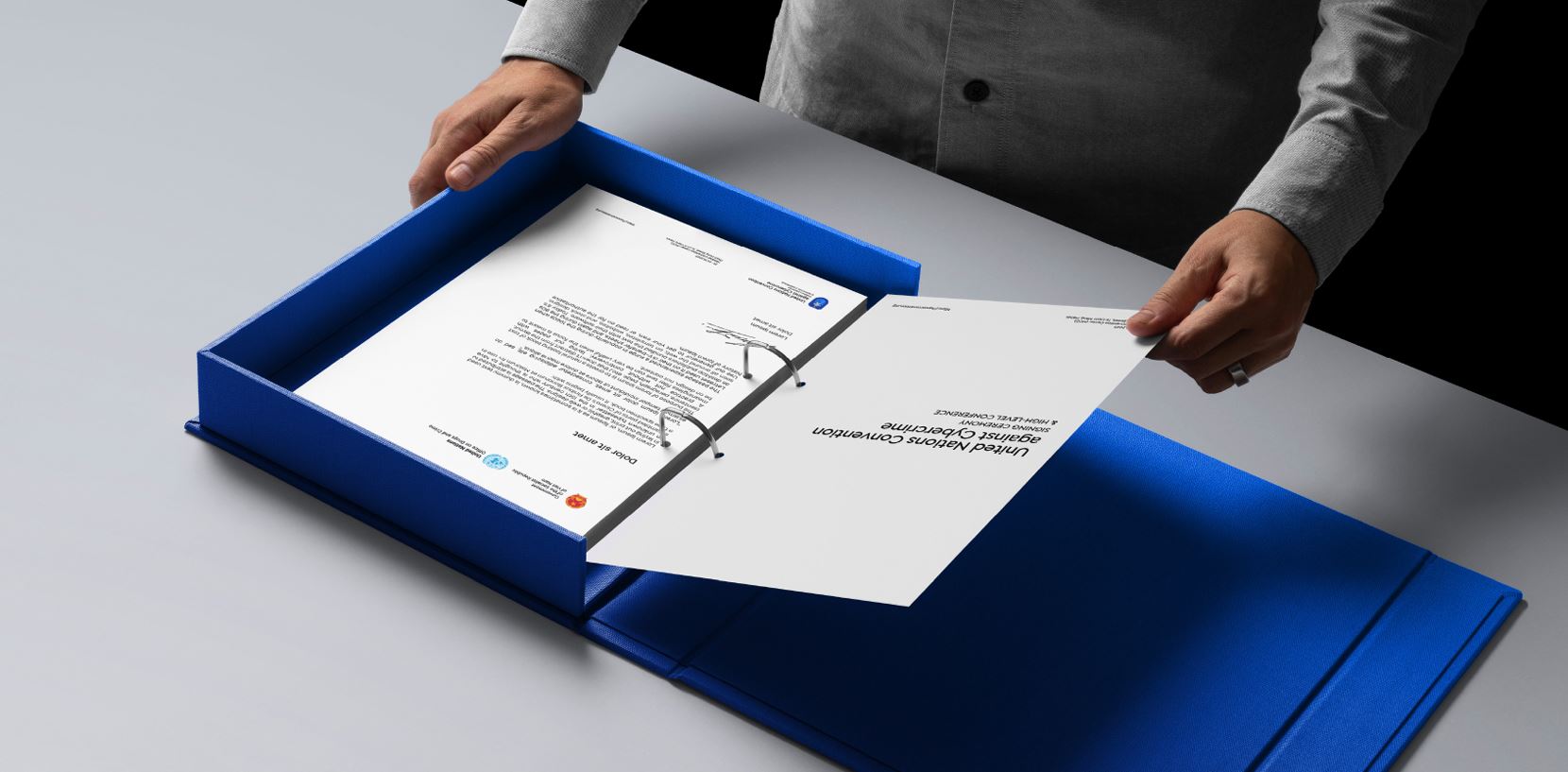
4. 国際協力
サイバー犯罪は国境を越えた現象であるため、国際協力はハノイ条約の柱と考えられています。加盟国は、サイバー犯罪の捜査、訴追、資産の回収、裁判において相互に支援することを約束します。
この条約は、各国が緊急に情報を交換し、容疑者を追跡し、電子証拠を保存できるようにする特別なメカニズム、つまり年中無休の通信ネットワークを確立します。
協力範囲はサイバー犯罪に限らず、すべての「重大犯罪」、つまり懲役4年以上の刑に処せられる行為にまで及び、電子証拠を共有する世界的な仕組みの形成に貢献する。
5. 注意事項
予防はサイバー犯罪との戦いの最前線であり、条約はそれを社会全体の共通の責任であるとみなしています。この文書は、政府、企業、学界、社会団体、インターネットユーザーコミュニティ間の調整を求めている。
この条約はまた、安全なデジタル環境を維持し、犯罪者の社会復帰を支援する際のサイバーセキュリティの専門家や研究者の役割も強調しています。
6. 技術サポートと情報交換
この条約は、対応能力を向上させるために各国間で知識、技術、経験を共有することを奨励しています。
優先分野には、デジタル調査員の訓練、早期警戒インフラの開発、サイバー脅威情報の共有、セキュリティ技術開発における民間部門との提携などが含まれる。
当局間の双方向の情報交換は、大規模なサイバー攻撃の早期発見とタイムリーな防止の鍵と考えられています。
7. 執行メカニズム
有効性と透明性を確保するために、ハノイ条約は国際レベルで実施を監視するメカニズムを確立しています。加盟国は実施の進捗状況を定期的に報告し、共同レビューメカニズムに参加して結果を評価し、経験を共有し、改善を提案する必要があります。
国際調整機関は技術支援を提供し、協力を促進し、対話と主権の尊重の原則に基づいて当事者間の紛争を解決する。