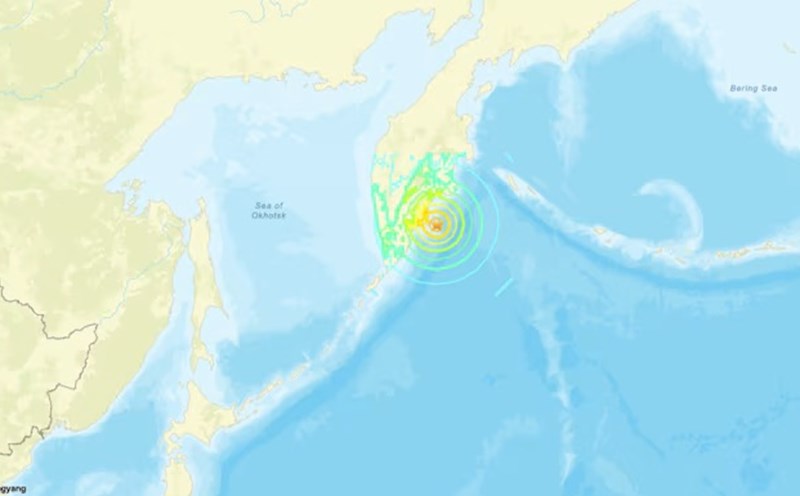9月26日、日本政府地震調査委員会は、今後30年間でナンカイ地帯でスーパー地震が発生する確率が80%から約60〜90%に調整されたと発表しました。
その理由は、日本の研究グループが、太平洋沖のナンカイ溝近くで毎年発生する海底沈下現象を発見したと発表したためです。このプロセスが記録され、超地震と津波のリスク評価の方向性が開かれるのは今回が初めてです。
日本の海洋・地球科学技術機構(JAMSTEC)の研究者であるユヤ・マチダ氏が率いるグループは、ドネット海の地震・津波観測ネットワークに属する水圧計を使用しました。測定は、日本の中部のキイ半島沖の2つの場所で行われました。
結果は、キイ半島南東部の海底が年間約1cm沈下し、南部では最大2.5cm沈下していることを示しました。これは、高度な精度を持つ移動式水圧調整装置とレーザー測定を組み合わせて、わずかな高さ差を記録し、その後6ヶ月から1年のサイクルでデータを比較することで発見されました。
ナンカイ峡谷では、海洋帯が大陸帯の下に沈み、海底を徐々に低くします。このエネルギーの蓄積プロセスは、帯域の境界の突然の滑りにつながり、大規模な地震や津波を引き起こす可能性があります。帯域の境界は固定されておらず、時々わずかな衝撃を引き起こすだけですが、スーパー地震が発生する危険性は依然として存在します。
日本気象庁は、ドネトデバイスを使用して津波を検出しており、水圧を波の高さのデータに変換することに基づいています。この新しい発見は、海底沈下と自然災害の危険性との関連性をより明確にし、早期警戒能力を強化するのに役立ちます。
Machida氏は、将来的には、研究グループが水圧調整装置の設置場所を拡大し、長期的な沈下傾向をより明確に特定し、それによってこの地域の大規模な地質災害の予測能力を高めることを期待していると述べました。